住み替えで家を移るとき、悩んだのが「子どもの学校」のことでした。
私たちの場合、引っ越しによって学区が変わり、本来であれば転校しなければならない状況に。
でも、子どもの強い希望もあり、私たちは「学区外通学(=越境通学)」という道を選びました。
この記事では、その理由と実際に行った手続きの流れ、そしてその過程で感じたことをまとめました。
なぜ「学区外通学」を選んだのか
まず、私たちが学区外通学を希望した理由は、子どもがそれを望んでいたからです。
私から見ても、
- 子どもがよい友人関係を築けている
- 先生との信頼関係ができている
- 近隣でも学校の評判がよい
という印象でした。
そのため、「できる限りこのまま通わせてあげたい」という気持ちがありました。

とはいえ、学区外通学は簡単に認められるものではありません。
「学区外」というキーワードで検索してみると、「学区外 裏ワザ」なんて出てきたりもしますが、私たちは正攻法でいってみようと、まず電話で教育委員会に確認してみました。
すると、「友達がいるから」「希望の部活があるから」などの感情的な理由では申請は通らないとのこと。
ふわっとした理由ではなく、審査を通すための根拠づくりが必要だとわかりました。
だからこそ、学区外通学を申請する理由をしっかりと準備して臨むことにしたのです。
学区外通学の申請フロー
私たちの住むエリアでは、学区外通学の申請先は教育委員会(学務課)でした。
手続きの流れ
- 自治体ホームページで「学区外通学の許可基準」を確認
- 教育委員会(学務課)に相談
- 申請書類の準備・提出
- 学務課での面談
- 教育委員会での会議・審査
- 許可通知書の受取
職員の方いわく、申請書の内容は会議で審査されるとのこと。
つまり、「気持ち」だけでなく、通学距離や子どもの特性など、具体的な根拠を提示することがとても大切でした。
実際に提出した申請理由

私たちが提出した申請理由の一部を紹介します。
通学範囲内であること
転居先は希望する学校から●km以内に位置しており、徒歩での通学が可能な範囲内であることを確認しています。そのため、安全かつ現実的な通学が可能であると考えています。
友人関係の維持が子どもにとって重要であること
現在の友人たちとのつながりを維持することが、学校生活の安心感や充実感を高める上で非常に重要だと考えます。
環境の変化に対する精神的な負担の軽減
子どもは新しい環境に馴染むのに時間がかかる性格であり、転居など環境の変化が重なる中、友人たちと同じ学校に通えることは子どもの不安を軽減する助けとなります。
これらの理由を具体的に、かつ教育委員会が納得しやすい形で書類にまとめたことが、審査を通過できた要因のひとつではないかと思っています。
子ども自身の強い希望も後押しに
私たちの家族の場合、子ども自身が「今の友達と同じ学校に通いたい」と強く希望していて、その気持ちを尊重したい、というのも私たち夫婦の共通の思いでした。
学務課の方との面談の際に、子どもの口から希望を伝えられたことも、大きな後押しとなったと思います。
審査結果が出るまでは、親子ともに不安な日々でしたが、許可通知が届いたときは本当にホッとしました。
結局、元のマンションに戻ってきたので、学区外通学をした期間は短いものでしたが、徒歩で通学できる範囲での学区外通学だったので特に負担は感じていませんでした。
学区外通学を考えている方へ
住み替えを考えるとき、学校のことは見落とせない要素です。
引越しによって学区が変わってしまうとき、必ずしも「転校」しか道がないわけではありません。
自治体のルールをよく調べた上で、「学区外通学」という選択肢もあります。
そして、審査が厳しい自治体の場合には、感情的な理由ではなく、客観的な根拠を丁寧に示すことがとても大切です。そのためには、教育委員会の方に相談してアドバイスをもらうこともおすすめです。
何より大切なのは、子どもの気持ち。
引っ越しや学校の変化は、大人が思う以上に子どもにとって大きな出来事です。
住み替えによって子どもの気持ちを置き去りにしないよう、じっくり話を聞く時間をつくって寄り添うことが大切だと思いました。
この記事が、同じように悩んでいるご家庭のヒントになれば嬉しいです。
▼ランキング参加中!ポチッと「イイネ」してもらえると励みになります![]()
にほんブログ村
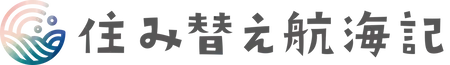

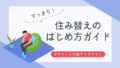
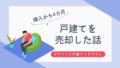
コメント